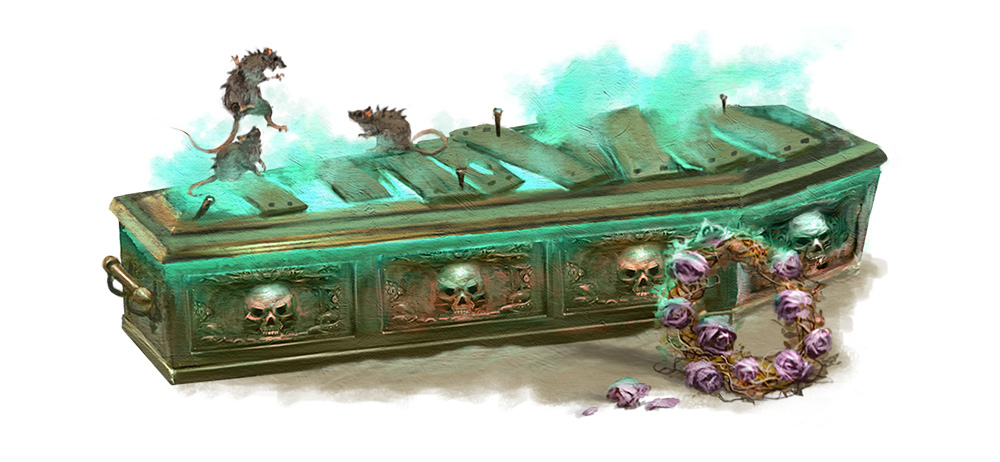古き罪
「旦那様、年老いた朝びらきにパンを恵んでくれませぬか?」
ダノス・タンガルトは最初、他のことに気を取られていて男の言葉が全く耳に入っていなかった。前日前夜続いた桁外れな雪嵐に気を取られ、評議会の集まりに遅れようとしていた……ほんの一分二分であったとしても無駄にはできない。検察官タンガルトは遅刻というものを何よりも嫌っていた。
「年老いた朝びらきにパンを恵んでくれませぬか?」
タンガルトが顔を上げると、入り組んだ路地の向こう側に立っている影が見えた。一体誰なのか、絶え間なく吹き荒れる雪に、暗い外套に身を包んだその姿は半ば隠されていた。タンガルトは足を止め、腰に下げた宝石付きの短剣に手を伸ばす。ピックマンスパイアのような辺境の小さな町では通り魔は滅多にない、が……ない訳ではない。それでも彼はさほど警戒していなかった。フリーギルドに十年も務めれば、誰しも鋼鉄のような胆力が身につくものだ。
「金もなければ、一滴の生命の水も持ち合わせておらん」彼は厳しく言った。「もし盗みを企んでいるなら、今夜は簡単には獲物は見つからんぞ。そうでないなら、どいてもらおう」
返事は無かったが、金属の擦れ合う音がした。タンガルトの短気な気質が頭をもたげ始める。この放浪者には不吉な気配があった。背を丸めひどくみすぼらしい……骨ばった手を繋いでいるのは手錠ではないか? 吹きすさぶ雪のせいでよく見えない。ヴェルディアの冬の冷気の過酷さ以上の何かが彼の心を震わせた。
「道を開けよ」さらに大きい声で彼は言った。「おどきなさい、さもなければ牢屋へ送ろうぞ」
風が唸りを上げた。その人影は掠れたため息をついた。
「デスマーシュ……」人影は言った。「戦いが終わる前に。空腹を満たすためにほんの少しのパンくずを求めただけのこと」
タンガルトの口の中がからからに乾いた。
「なんと言った?」彼は息を詰まらせた。
次の瞬間、タンガルトは我を忘れて人影に向かって長刃のナイフで斬りつけていた……何をしているか分からないままに……無我夢中であっても、刃は確かに男の顔を、外套に隠れていようと切り裂いたはずだった。だが手応えはなく刃は空を切り、タンガルトは勢い合ってよろめき膝をついた。
顔を紅潮させ目を見開いたまま素早く立ち上がったが、路地には誰も残されていなかった。放浪者は消えていた。そこには、雪の上に一枚の金属の円盤が残されていただけであった。コイン・マレウス……朝びらきの戦士の印章である。その徽章を見つめるうちに不安が胸を打ち鳴らした。長らく封じ込めていた記憶が、羞恥と嫌悪を伴う波となって意識の底から浮かび上がる。タンガルトは両の目を閉じ、二十年もの間、燻ぶらせていた記憶を魂の底へと押し戻した。
彼が目を開けると……そのコインも同様に消えていた。

苦悩は一日中まるで影の様にタンガルトに付きまとった。評議会に出席し、求められるままに発言はしたが、一つ一つの言葉が燃え殻のように口から零れ落ちた。(そうだ、徴税は十分に進んでいる)(ああ、グレイウォーターからの最新の通信では、煙粉爆弾の積荷はハロウズウォッチまでには到着するそうだ、シグマーの御心のままに)周囲の視線に懸念が宿っていることには薄っすら気づいていた。いつもなら、このような議会は検察官タンガルトが推進し、この拠点の指導者として厳しく追及するのが常であった。通常は主導権は彼にあるのだ。
その日、タンガルトはほとんど言葉を発することができなかった。
デスマーシュ……ハンマーハル・グューラ第百九十三連隊の必死の攻防戦。あの地獄絵図での悪夢を真に忘れ去ることはないだろう。生き残るために自らが行ったことの記憶もまた……あの奇妙な放浪者との遭遇は、疲弊した心が見せた幻だったのだろうか? だがあの言葉……現実であったように思う。
彼は体調不良を言い訳に議会を早々に抜け出した。雪はさらに激しさを増し、場所によっては膝のあたりまで積もっている。家々の軒下からは短剣ほどの長さの氷柱が垂れ下がり、風が窓板を激しく打ち鳴らし屋根瓦を鳴らしていた。たまに外套を体に巻き付け家の温もりを求めて足早に雪をかき分ける人々とすれ違った。タンガルトは吹きすさぶ風に頭を下げ、足を取られることなく歩いた。休息が必要だった。それだけだ。
彼の屋敷はこの砦で最も大きく、醜く無秩序に拡大したピックマンスパイアを見下ろすなだらかな丘の頂にあった。ようやく玄関に辿り着き、扉を開けると、酷い突風に漂う氷の欠片が室内へ舞い込んだ。タンガルトは声を漏らしながら扉を強く引いて閉めた。部屋は暗闇に包まれている。
タンガルトは扉に額を当てて深く息を吸い込んだ。
二階から金属のぶつかり合う音が響き、続いて足音がどすどすと聞こえてきた。タンガルトは立ちすくみ、胸の内で心臓が激しく鳴り響く。視線を素早く階段へと走らせた。
物盗りめ。
暖炉の上には、かつて騎士であった頃のピストルがまだ掛かっていた。彼は素早くそこへ向かい、保管庫から手探りで火薬と弾薬を取り出し装填した。古い銃を手に勇気が込み上げてきた彼は、階段へと向かった。途中で食卓から蠟燭を掴み、外套のポケットにいつも忍ばせている黄鉄鋼の火打石の欠片で火を灯した。
「誰だか知らんが、聞け!」彼は手すりの隙間を銃で狙い、一段ずつ階段を上りながら叫んだ。「ここから立ち去れ、さもなくば縛り首だ! 」
踊り場に辿り着くと、蠟燭が薄暗い廊下を橙色に染めた。彼の居室の扉は開いていて、戸口にはガラス片が散らばっていた。タンガルトは背中を壁に押し付け少しずつ進んだ。扉の縁まで着くと、一瞬息を整え、寝室へと飛び込み、室内での動きの兆しを探ろうとする。
部屋は空っぽであった。奥の窓が開いていて、風が吹くごとに壊れた窓枠が壁にぶつかり音を立てていた。床の絨毯は吹き込む氷の欠片で白く覆われていた。燭台が雪に覆われた足元を行ったり来たり転がっては音を立てていた。
タンガルトは窓へと近づき、吹き荒れる白い雪雲の向こうを覗き込んだ。もし何かが動いたとしても彼の目には見えなかっただろう。多少の力を要して、彼は窓を押し上げて掛け金をかけた。外では嵐が猛威を振るっているが、タンガルトの屋敷は再び静けさを取り戻した。不気味なほどな静寂……その静けさはまるで死刑執行人が斧を振り下ろすのを観衆が待っているかのような不快な情景を思い出させた。
「年老いた朝びらきにパンを恵んでくれませぬか?
タンガルトは反射的に振り向き考える前に発砲していた。居室は火薬の閃光によって一瞬照らされた。外套の影が戸口に倒れ込み床へ崩れ落ちた。人影は倒れたまま荒い息をしている。

タンガルドの震える手から拳銃が滑り落ちた。しばらくの間彼は立ち尽くしたまま息を整えようとしていた。痺れた脚を無理やり動かしながら、横たわる侵入者に近づく。床では血液と雪解け水が混ざり合っている。タンガルトは屈んでそのフードを引き下ろした。その容貌を見た瞬間、胸の奥に氷の欠片が突き刺さった。
「イグナン?」
そこに横たわっているのは、かつての友であった。だが、そんな筈はない。イグナンはデスマーシュの戦場で、泥だらけの砲弾のクレーターの中で死んでいる。二人は八日間もの間、腐臭漂うあの地獄を共に過ごした。手元には半分ほどの配給缶と錆びた水の数滴だけ。あの呪われたドゥアーディンの砲撃が絶え間なく轟き続ける中、二人の理性は砕け散った。最後の腐った欠片を奪い合うため悪魔の様に戦ったのだ。
「パンを恵んでくれませぬか?」イグナンのようなナニかはべらべらと話し、唇はめくれ上がり黒ずんだ歯がさらけ出された。
タンガルトは今も昔も容赦がなかった。そう、彼はイグナンの喉元を切り裂き、血が流れ尽きるのを見ながら最後の一片のライノックスの酢漬けを貪り食ったのだ。
イグナンの濁った虚ろな眼は眼窩の内でぐるりと回り、悲し気な眼差しを彼に向ける。
「腹が減ったんだ、ダノス。ここは暗くてとても寒いんだよ」
恐慌がタンガルトを支配した。逃げようとしたが、亡者は異様な速さで立ち上がり階段への道をふさいだ。その姿はゆらめき、形を変え、長すぎる前肢から鎖の音が鳴り響く。それは鉤爪の手を振りぬき、タンガルドは前腕を抉られよろめく。まるで氷水の桶に腕を突っ込んだかのように傷が痛み、冷気が体の奥へと広がり心臓を突き刺した。
息を荒げ、胸を押さえながら、タンガルトはたった一つの逃げ道を探した。寝室の窓を勢いよく開け放ち、窓枠にはい上がる。一瞬躊躇ったが、イグナンのようなナニかがその目を翠玉のように燃やし、喉元を狙って鉤爪を伸ばし這ってくるのを目にして心を決めた。一部露出した黒衣の下にはもはや友の容貌はなく、骸骨のようなデスマスクであった。
タンガルトは凍てつく夜へと身を投げた。彼を引きずり込みに来た恐怖の亡者に抱かれながら空中で身をよじっていた。
「許してくれ!」幽鬼の指が喉笛を絞めるなか彼は絶叫した。
ダノス・タンガルトは肉体の苦痛は、彼が下の鉄柵に突き刺さったときに終焉を迎えた。しかし彼の壊れた魂の苦しみは永遠に続くだろう。
翌日、フリーギルドの巡視員が検察官の砕けた遺体を偶然発見した時、彼を死へと突き落としたのが誰だったのか、何があったのかその兆候を示すものは何もなかった。唯一残されたのは、生気のない掌に押し込まれた古い朝びらきの戦士のコインだけであった。